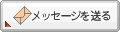› 家にかえる・・・ › 豆づくしランチ
› 家にかえる・・・ › 豆づくしランチ豆づくしランチ
2024年08月22日

パレット地下。
ふる里さんは何年振りでしょう。最近は数年ぶりに訪れた店に驚いたこと(残念)がありましたが、
ここは相変わらず島んちゅにも観光客にも人気の故郷料理。
ジーマーミ豆腐、うの花、ゼンザイ、アオサ豆腐汁、湯葉煮つけ、豆乳ドリンク。。
画像からアオサの色がはっきりしませんが、たっぷり入った具は嬉し~
この豆づくしはTV紹介があったと記されています。そうなのね~天ぷらも上手に揚がっていますよ。
相棒のイナムルチも具沢山なのです。

亡き母と行ったのが4年前?最後だったかしら。
母と娘
のランチは珍しくもなく、私は息子らしき人が母親と食事をしている光景が大好きです笑
その母は、コロナ禍になって、相続人がホーム入居手続き。本人も嫌とは言えず承知したのでしょう。
寂しさからおかしくなってしまい、届いた祈りも夢でみたことを母自身が報告してくれたのに、段々、環境にも体力にも追いつけなく、それさえも信じなくなった母。
己に負けてしまったと残念で、その憑依された様子を認知症と勘違いした家族は苦笑いしていた。
先祖供養では、やりすぎると未浄化霊を引き寄せてしまい、
障りを自ら引き受けることになることもあるということらしですね。
霊的真理を知らなければ、この世的なことに飲まれていくだけです。
霊感、霊媒体質だと、頼られることもあるようですが、
学びの上から、生きている人も亡くなった人も
魂の修行は続くため、魂の向上に繋がらないことには関与しないようにしました。
避けては通れないことを片付けられないのはあの世に持ち越しなのですね。
亡くなって終わりではなく、生きている人が亡くなったことを自覚させ(お経ではない、それを理解できていないし、、わからないのにすがりつく?)難しい仏教もわかりやすい八正道だけでも理解しよう。日常生活の規範になれる。
煩悩が強く、それが邪魔してあがれないことはよく聞く。
お経や線香で解いたり浄化したりはできず、故人の上がれなかった問題を知っているはずの家族が亡くなった個人へわかる言葉で諭してあげることだということでした。どういう執着や未練をのこしているか、家族なら知っているわけです。
行く先でも修行がはじまることも、生きている人が光へ戻れるよう、
普段の言葉で促すことのようですね。
知識や教養、資格でもなく、家族であれば家族なりの供養はできることなのですね。
ただ、故人から「おまえにいわれたくない」と反撃されないよう、自分自身も魂の磨きをしておかなければ。。うんうん
(母を霊界から上げられるところまで上げてみましたら、行く先はのどかな田園風景でした。
これもやってみたいと導師に伝えると、用心してと注意。できるかどうか無茶はいけませんね。この場合はその場所でよかったようです。やってあげる、、でもないようです。これは守護する方々の支援あってのこと、お連れする場合は道連れにならぬよう守られていないといけません。セルフヒーリング、セルフコントロールが基本であり、それができるよう授業を理解していないと、家族への導きは慢心や誤作動で道からずれてしまいます。こういうこは、あくまでも相手にも上がりたい気持ちと反省が現れた場合ではないかと相乗効果が結果だと思いました)
授業の先祖供養シリーズは大変納得いくものでした。
手放しは物質だけではなく、歪んだ観念も習慣も必要ですね。
面白い記事を見つけました。わかりやすい例えは授業でもありますが、
この類のことを理解できるように、誰にでも道は開かれて学べるようになっています。
子を亡くした女性にブッダが"冷たく"接した理由 「諦める」は、仏教では「明らかに見極める」
知識もあって、霊的真理も理解できれば幸いですが、
私は言葉や文字を話せず、云わんとすることを見つけたり、
ネガティブなサイトやそのエネルギーは見るに耐えないので選別しています。(これも授業から得た感覚です)
『ゴータミーは貧しい家からお金持ちの家に嫁ぎ、子どもも産まれて幸せな日々を送っているのに、ある日その子どもが病気で亡くなってしまう。悲しみのあまりその子の遺体を抱えたまま、出会う人ごとに「この子を生き返らせてください」と無理なことを頼みながら町中をさまよっているときに釈迦と出会う。
釈迦は「死者を出したことのない家に生えている芥子のタネを持ってきたら、それで生き返らせる薬がつくれるだろう」と言って、ゴータミーはすぐさま町中の家を訪ねて芥子のタネを探しまわるわけですね。死者を出したことのない家なんてないのに探してこいなんて、ひとつ間違うと釈迦が超意地悪に取られちゃうじゃないですか。
ゴータミーは、子どもが死んでしまったことを頭では理解しているでしょう。でも心が受け入れられないのです。いくら探しても、死者を出したことのない家の芥子のタネが見つからず、意気消沈して戻ったゴータミーに、釈迦は「死者を出していない家などない。人は皆、死ぬ定めである」と言い、ゴータミーはこの言葉で初めて、子どもの死を納得して受け入れることができたとされています。誰にでも死は訪れるということを、実際に自分で体を動かして家々を訪ねてまわることにより、初めて実感として理解したという話だと思いますね。
「諦」という漢字に「真理」の意味がある
見せかけの優しさで慰めれば、その場を一時的には丸く収めることができたのに、釈迦は苦い真理をしっかりと教えましたよね。日本語で「諦める」は放棄や断念など、ネガティブなイメージで使われることが多いと思いますが、仏教では「明らかに見極める」ということですね。
仏教では「諦」という漢字に「真理」の意味があると考えます。釈迦の重要な思想であり、仏教の基本方針に「四諦八正道」というものがあります。四諦とは「苦諦・集諦・滅諦・道諦」の4つの真理。八正道とは、煩悩を消滅させるための具体的な8つの道。すなわち苦しみから逃れるために、正しい心を実現するためのトレーニング法です。ゴータミーはその後、釈迦の弟子になりますから、釈迦の指導によって本当に救われたのでしょう。
「渇愛」とはで、喉の渇きに耐えかねた者が激しく水を求めるような、強い欲望や執着を意味します。だから渇愛というものは、つねに不満や苦しみを伴うのです』
そのような状態から抜け出るために、瞑想の日があります。煩悩や苦悩をどうクリアしていくのか、霊的真理も知らないと
自分なのか、他人を生きているのかさえわからなくなります。
どんなに言葉巧みに並べた心情も、導師の見抜き、見極めるやさしさと導きには、どうしても反論できません。
(神聖な存在に反論できない、神聖と気づくのも瞑想での光体現)
教えてくれる人もいなくなれば、少なくなれば、私達の住む大地すら守っていける人間は減っていくことになります。
あれこれ発信するものにも、注意しその真偽も聞かなくては困ることになりそうです。
真実、事実を知るのは勿論ですが、自分自身の真実こそ、過去世より今を正しく、楽しく生きていくことは
魂の成長であり、なにより大事なことだと自覚できましょう。
陰謀論に振り回され、精神を病むことや迷いだらけになるものが増えることも後を絶ちません。
肉体をもってのアセンションはないでしょうし、今生きている人の魂の修行後の行く先は新しい地球へと努力し協力していきたいと思います。
Posted by kiyoko at 07:22│Comments(0)
★連絡やコメントの公開を望まない場合は、そのように対応します。